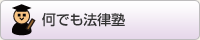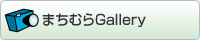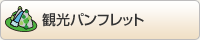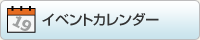何でも法律塾

掲載された文章・画像等の無断転載を禁止します。著作権は宮崎県町村会またはその情報提供者に属します。
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ①」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
私どもが今後の訴訟社会(法的社会)で安全に生活していくための方法や具体例のお話しを、特に高齢者が遭遇し易い事例を中心に、数回に分けてしていきたいと思います。 市町村職員の皆さんも、自分の地域の高齢者が被害に遭わないように、高齢者被害防止策を心がけて欲しいものです。
【訴訟社会・法的社会とは】
社会内のトラブルを裁判によって法的に解決しようとする傾向の強い社会、また、一般に訴訟が多く日常的である社会を指します。我が国が規制緩和政策を基本に自己決定・自己責任原理の社会を目指す方向になれば、トラブルは自分で解決しなければならなくなるので、訴訟社会へ移行していくことになります。
1. 高齢者を狙う詐欺的商法や振り込め詐欺(俺々詐欺)
(1)高齢者社会と高齢者の貯蓄資産
今、日本は超高齢化社会と言われています。高齢化社会とは、総人口に対する65歳以上の老齢者人口が多数を占める社会をいうのですが、その割合が7%~14%だと高齢化社会、15%~20%だと高齢社会、そして21%以上だと超高齢社会といいます。日本は、昭和45年に高齢化社会、平成6年に高齢社会となり、つい最近の平成19年に超高齢社会となりました。今では、5人に一人以上が65歳以上であるという人口比率になっています。団塊の世代(1947~49 年生まれ)が65 歳に達する2012~14 年には国民の4人に1人が65 歳以上の高齢者となる見通しです。
また、少し古いですが、私の手元にある「平成17(2005)年完全生命表」によると、平均寿命(0歳における平均余命)は、男78.56年、女85.52年となっており、年金生活が13年~20年くらい続けられる時代になっていますし、高齢者人口のうち、男性の8%、女性の18%が独居生活をしているとの統計結果(平成18年高齢者白書)もあります。
そして、最も重大な要素は、高齢社会と同時に少子化社会(出生率の低い社会)になっていき、高齢者層の年金制度が維持されていくと、家計の貯蓄が高齢者に集中する構図が一段と進む見通しであるとされています。
すべての団塊の世代が60歳となる09 年には、60 歳以上の世帯が保有する貯蓄額のシェアは60%程度まで上昇していき、高齢者ほどお金を持っているという社会になっていきます。
高齢者がお金持ちになるというより、若い人の負担が大きくなり、若い層の人がお金が無いという状態になるので、高齢者層がよりお金をもっているように見えるということでしょう。
(2)高齢者をターゲットにした悪徳商法
高齢者が多くなり、その高齢者がお金を持っているということになれば、市場原理として高齢者がビジネスや商売のターゲットとなるのは当然だということになります。高齢者の生活に必要な商品開発や商品販売が盛んになることは好ましいことですが、高齢者の知識不足や判断不足に付け込んだ「悪徳商法」が横行しています。訪問販売などでの押売り商法などがその典型例ですが、二、三紹介しましよう。
①点検商法
ある日、70歳一人暮らしの太郎さんの家に、リフォーム業者が訪ねてきて、「福岡からきた○○工務店です。うちはシロアリ防除資格がありまして、今回、九州一円の宣伝活動として、宮崎地区を担当して、無料で床下の点検サービスで近所を廻ってます。お宅の床下の点検も無料でしますので、いかがですか?」と宣伝して、床下に入って点検し、「シロアリに蝕まれていますね。」とポロライド写真を見せて、薬剤貼付と薬剤散布を20万円で勧められたので、現金で支払って工事してもらうことにした。薬剤は即日床下に散布された。後日、花子さん宅を立てた大工さんに話をしたところ、床下の点検をしてもらったが、シロアリ腐食箇所はまったく無かった。騙されたが、業者の連絡先もわからず、名刺や領収書の住所にはその会社は存在していなかった。
これは、「点検商法」と言って、サービスで点検してあげますということで信用させ、点検して問題点を指摘して、自分の買わせたい修理商品や補正剤などを売り込むやり方です。特に地元業者を語らず都会の業者であるとすることが多く、その点で不審な点があるのですが、専門家による点検がサービスならば、誰でも受けたくなるという心理を利用しているものです。また、よその会社であることに疑問を持たれたら、その地元の有名業者を調べていて、「現在、宮崎地区の連携業者として、○○建設ともお話しをしている会社です。」と地元業者の名前を勝手に使って、その信用を利用することなどをしたりしています。
この商法は、虚偽の事実を告げて契約させていますので、民法96条の詐欺として取り消し、又は特定商取引法に基づき契約日から8日以内にクーリングオフ(無理由解除)をして、代金額20万円を返してもらえるはずですが、業者名や担当者の所在が明らかでないとそのような請求すらできない状態になります。警察に詐欺被害として被害届をするだけで泣き寝入りになる可能性が高いです。
(次回の「②見本商法と次々商法」へ続きます。)
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ②」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前号に引き続き、高齢者の知識不足や判断不足に付け込んだ「悪徳商法」の例を検討していきましょう。
ある日、70歳一人暮らしの花子さんの家に、リフォーム業者が訪ねてきて、「屋根や壁などの細かな修理をしている会社で、この近所の家を見て廻っています。お宅の屋根をみましたら、そろそろ葺き替えなどのご注文はないかと思ってお立ち寄りしました。」と申し込んできました。断わったら、「じゃあ、うちの会社のパンフレットだけでもみてください。屋根や壁だけでなく、水周りの工事もしていますから。」と置いて行ったので、悪徳業者でもないみたいだと感じていました。
一週間くらい経って、同じ業者が、若い従業員を同伴して「うちの若手従業員の研修として、サービスで水周りの点検作業をさせていただいております。お宅の水周りの点検を研修としてさせていただけませんでしょうか?」と依頼してきたので、花子さんも無料ならどうぞお願いします。」と承諾しました。点検の結果は、水漏れはないが、水道管と風呂の排水管が腐食しているので替え時だという結果であったが、お一人の判断では難しいでしょうから、今すぐに管の取替え工事をするというわけにもいかないので、工事される場合には、うちの会社に頼んでいただくとありがたいです。」と言って、素直に帰っていきました。
その二日後に、電話連絡が入り、「お宅の水周りの件ですが、管の取替え工事をしないで、お風呂全体を取り替えてみませんか?丁度、明日からキャンペーンが始まり、お風呂のモニターとして、お風呂の宣伝写真を撮らせてもらったりして宣伝モデルになることを了解していただける契約をすれば、ものすごくいいお風呂が、格安で設置できますし、配管工事も無料ですし、サービスで水周りの管の取替えもできます。お伺いしてお話しを聞いてもらえませんか?」と申入れがあり、信用できる親切な業者さんとのイメージを持ち始めていたので、訪問してもらって、200万円の契約を150万円にしてもらい、業者の持参したローン契約書で契約して、風呂の改修工事をしてもらいました。
その後、その担当者は、風呂の掃除をしてあげたりしながら、「風呂工事の際に床下点検をしましたが、耐震構造になっていないので、家が危険な状態です。あなたの身の安全のために、耐震構造の処置ができる友人を連れてきます。相談してみてください。」と言ってきて、翌日、その友人が「やはり危険な状態なので、床下工事したほうがいいですね。耐震部品を付ければ、30年くらいは地震にも問題ない構造になります。」と説明して、耐震部品の購入と付加工事をローン契約しました。
その工事が済んだら、担当者が、お風呂のモニターの話をするとの口実で、工事の御礼やお土産のお菓子などを持ってきたりして頻繁に花子さんの話し相手になったりしていました。花子さんは、地震の心配をしてくれたり、お菓子を持ってきたりしてくれるので、すっかり信用するようになり、ある日、「おばあちゃんも、子供夫婦やお孫さんとなかなか会えないで、独り生活は寂しいですね。」と慰められて、その担当者が「やはり、家は屋根が命です。最初お知り合いになったのも、家の屋根が気になったからです。屋根の葺き替え工事をしましょう。床下の耐震だけでは、まだ不安が残りますので、独り暮らしのおばあちゃんのためには、万全を期したほうがいいですよね。」と屋根の改修工事を持ちかけてきて、ローン契約は二つもしているので、預金や蓄えから500万円ほど都合してもらえれば、家全体の悪いところの修繕もしますということで、屋根修理契約をして、預金から500万円を支払いました。
しかし、工事内容は、屋根の葺き替えではなく、瓦の塗装を塗り替えるだけの杜撰な工事で終っていたこと、風呂の工事も、耐震床下工事も、通常の5倍~10倍の代金でのローンを組まされていること、業者の所在地には業者がいないことが消費相談で判明しました。
これは、見本商法に始まり、一度の契約をすると短期間に次々に不要な契約をさせて商品や工事を購入させる「次々商法(つぎつぎしょうほう)」の例です。
このような冷めた親子関係にある独居高齢者を悪徳商法のターゲットにするマニュアルがあるようです。それによれば、
A まず、独り住まいの高齢者の家に上がり込む方法を考える。サービス・無料で信用させ、最初から無理強いはしない。
B 家に上がり込むことができたとしても、自分からは話さず、高齢者の話相手になって話を聴いてあげる。
C 子供さんの代わりに高齢者の生活を心配して、専門業者として助言しているように思わせる。
D 危険を誇張して、早急に工事したりする必要があると思い込ませる。
E 短期間に次々と契約をしておく。
F 高齢者が信頼するポイントは、
ⅰ>掃除をしてあげる。
ⅱ>お土産を持参する。
ⅲ>擬似親子関係をつくる(「実際の子供さんの代わりに」と説明する。)とされています。
このマニュアルには、今の日本の独居高齢者の心の隙間を悪用する意図が表れています。他方高齢者のほうには、騙される寂しさがあり、騙された結果、実の子供に叱責される姿が想像されます。唯一の蓄えも使って、家を修繕したのは、実の子への相続財産の補完でもあったはずなのに、その子から怒られる。「自分の蓄えを自分の判断で使って何が悪い!」と内心で自分を慰める高齢者の心情も窺えます。
最終的には、高齢者は、時間が過ぎていけば契約時のことを忘れてしまい、契約書自体も失くしたりしていて、面倒くさい解決手続も嫌う傾向にあります。そこで、泣き寝入りする場合が多くなります。ここに、悪徳業者が高齢者を狙う理由のひとつがあります。 (次号に続きます。)
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ③」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
悪徳商法への未然防止策としては、具体的な被害例を聞いておくことが有効ですので、前号・前々号に引き続き、高齢者の知識不足や判断不足につけ込んだ「悪徳商法」の例を検討していきましょう。
今回は「利殖商法」の例です。
③利殖商法
- 高齢者は3つの大きな不安 = 「お金」の不安、「健康」の不安、「孤独」の不安を持っていると言われています。それゆえに、この3つの不安を解消してくれるような話(商法)には、関心を持ってしまい騙される傾向があります。
「お金の不安」は、手軽にお金が増えるというようなマルチ商法や利殖商法に騙される素地を作っており、「健康の不安」が健康布団や健康薬品等の訪問販売に騙される素地を作っており、「孤独の不安」は、次々商法や催眠商法に騙される素地を作っています。
- 特に、老後の蓄えで生活している高齢者は、「お金の不安」から、まだ蓄えに余裕がある時期に蓄えを増やしておこうという投機的な利殖商法に騙される傾向があります。
利殖商法は、昔から、天下一家の会のねずみ講事件に始まり、有名なのは、金のペーパー商法であった豊田商事事件、「円天」という独自紙幣を利用したL&G出資法違反事件、東南アジアでのエビの養殖事業投資を唄ったワールドオーシャンファーム事件など、高利回り・高配当の利殖投資に参加して、蓄えの全財産を取られた高齢者の人たちも多いことは、皆さんもテレビ・新聞のニュース等でご存知のことと思います。
<利殖商法の具体例>
「ねずみ講」 ⇒ 「商品の販売は目的としないで金銭の配当だけを目的とするもので、無限連鎖講防止法で禁止されている手法を言います。
(例):「5万円で会員になってもらえば、その後、新たに会員を2名探して加入させると1万円の紹介報奨金が戻ってきますので、5人会員紹介で元が取れ、その後は会員1人につきお金が入るだけの状態となり儲かる制度です。5万円会員から5人紹介していただいた段階で、100万円会員コース、500万円会員コースに登録することが可能です。集まったお金で○○総裁が世界的に経営している10企業へ融資することで莫大な利益を生むことができるので、このような方法は、私どもだけ可能となっています。」として、最終的には500万円コースに案内し、会員費用500万円を受け取った時点で、会員紹介奨励金をなかなか支払わないようになり、そのうちに、組織が無くなった状態になり、500万円が全く回収できなくなった。
「マルチ商法」 ⇒ 物品・商品の権利・サービスを組織の上位者から下位者に販売し、更に下位者を会員に入れることで販売利益を連鎖的に得ることができる組織的商法であるのですが、連鎖販売法という方法で、ねずみ講とは、商品が動く点で異なるだけです。特定商取引法により連鎖販売業として規制されていますが、ねずみ講とは異なり禁止まではされていません。
(例):近所の保険外交員などをしているという女性から、「保険の話じゃないんだけど、いい話があるんですよ。月100万円くらいまで儲かる話があって、会員になると特別価格で健康食品が購入できて、それを知人や友人に勧めて売れたらバックマージン(手数料)がもらえて、知人や友人が会員になれば、紹介者として手数料比率が上がって、健康食品を買えば買うほど手数料がどんどん増えていくんですよ。」という話を真に受けて、貯金していた200万円を払って会員になったが、買ってくれる人を見つけられないまま、意味もない健康食品が大量に残り、他の会員を紹介することもできなかった。その女性も行方不明となり、200万円を取り戻すことはできなかった。
- 「うまい話にゃ、裏がある。」という話ですね。人間には限りなく欲というものがありますので、利得商法(もうけ話)には、特に気をつけなくてはいけないと思います。最初にお話しましたように、「不安」があるので、不安を解消し安心したいために、つい騙されてしまうということですから、悪徳商法にひっかからないためには、三つの不安の安全な解消法を探すことです。そもそも三つの不安を持たないのが一番いいのですが、それぞれが根本的な不安なので、宗教的に悟らない限り誰しもが不安を持たざるを得ません。このシリーズの後半で「未然防止策」を書く予定ですが、細々とした防止策よりも、まずは「高齢者は自分1人で判断しないこと」そして「高齢者を1人にしないこと(高齢者を孤独にしないこと)」が重要です。
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ④」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
引き続き、高齢者の知識不足や判断不足に付け込んだ「悪徳商法」の例を検討していきましょう。
東日本大震災が起こる前の平成22年暮れ頃から、「タイガーマスク」「伊達直人」などと名乗る人から、児童養護施設などに善意のプレゼント運動(タイガーマスク運動と呼ばれ始めました)が続いていますが、現実の社会の中では、そのような福祉への善意を逆手に取るような悪徳商法もあることを知っておきましょう。福祉を語るエセ福祉詐欺商法などです。その方法として、自宅に訪問してこないで、電話等で勧誘して契約させる悪徳商法が利用される場合があります。ひどい例では、電話もしないで、突然、高価な本や商品を送りつけてくる場合もあります。「送りつけ商法・ネガティブオプション」とも呼ばれています。今回は、その話をしましょう。
④電話等による「送りつけ商法」
(例) : ある日、70歳一人暮らしの次郎さんの家に、身に覚えのない会社から小包みが送られてきた。不審に思いながら、包みをあけてみると、「あなたの思いやりで、困っている人に盲導犬・介助犬をプレゼントしましょう。盲導犬・介助犬の飼育事業・訓練事業を立ちあげるために、同封のハンカチを購入していただける協力者を求めています。5000円で購入いただくことで、あなたの行為で、何人もの身体不自由な人が救われることになります。」と振込用紙が同封されていました。
次郎さんは、不審に思いながらも、福祉事業への協力なら少ない生活費から無理してでも協力しようと5000円を送金しました。
その後、すぐに、同じ会社から、北方領土返還運動の協賛事業であるとの説明書を同封した豪華本の小包みが送られてきて、「5万円の口座振込請求書」が同封されており、「福祉事業の多くの方々にもお買い上げいただいています。お読みになって不要な場合には、1週間以内にご返送ください。代金の支払いもなく且つ本の返送がない場合には、お買い上げいただいたことになります。」との説明が書いてあった。
次郎さんは、面倒くさいことは嫌なので、代金の支払をしようと思っています。
<対応の仕方>
① 相手側の仕組み
この次郎さんの例の場合には、最初のハンカチの「送りつけ商法」は福祉事業団体を仮想した虚偽の説明をしているものだと思います。まともな福祉事業団体であれば、普通は、チラシ送付かダイレクトメールなどで購入案内をして、申し込んだ人に品物のハンカチの送付をするはずです。ハンカチを購入しない場合の返送文言もなく送りつけるだけの方法ですから本当は非常識なやり方ですが、逆にハンカチはプレゼントと思わせて、善意の寄付金を求めているような形式を取っています。
また、送りつけ商法とまではいかない段階で、同封のハンカチをそのまま貰っている人のほうが多いかもしれませんが、これは、業者のほうでは多くが送りつけたままで終ることも覚悟した「駄目モト商法」というもので、払ってくれるものが一人でもいれば、それはそれで損はしないということを計算しているものです。
そして、このハンカチ購入をした人(代金を振り込んだ人)に対して、その情報に基づいて、今度は本気で「送りつけ商法」を始めるのです。業者から見ると、ハンカチを購入した人は真面目でお金のある人なわけですから、社会福祉や国の政策への協力に嫌とは言えないやさしい人として見抜かれて、今度は、断れないような正義事業の名目で、高額な本の購入を求めるのです。後の「豪華本」は完全な「送りつけ商法」です。
② 対応方法とその基礎知識
ここでの相手方の説明書には、法律上は完全に間違っていることが書かれてあります。「代金の支払いもなく且つ本の返送がない場合には、お買い上げいただいたことになります。」との記載です。法律上は、勝手に送られてきた本を1週間以内に返送しなくても、買ったことにはなりません。
物の売買契約は、売ろうとする「申込」に対して買おうとする人が「承諾」をすることで契約成立となります。業者が本を送りつけたことは、本の売買の申込であり、こちらはまだ「買う」という承諾をしていません。本の売買契約は成立しないままで、本がそこにあるというだけで、契約成立で発生する代金支払義務は全く発生していません。「本の返送がない場合には、お買い上げいただいたことになります。」という文言は全くの嘘です。次郎さんは、本の代金を払う必要は全くありません。
じゃあ、手元にある本はどうすればいいのか? ということですが、本はまだ送り主である業者に所有権が残っていますので、次郎さんは勝手に処分できません。しかし、法律(特定商取引法)で、送付されてから14日経過した後(返還請求の連絡をした場合には、請求から7日が経過した後)には、こちらで勝手に処分できるとの規定がありますので、次郎さんは、その本を捨てて構いませんし、送り返さずに自分の手元にそのままにしておいても構いません。
なお、自分の手元に置いていたり、捨てたりするのは気持ちが悪いと思う人は、相手方の着払いでもこちら払いででも、相手方に返送すること自体は何ら問題ありませんので、送り返すことも当然できます。
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ⑤」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
高齢者をターゲットにした悪徳トラブルとして、日本の社会で大きな問題となっているのが「振り込め詐欺」(「オレオレ詐欺」とも言われていました)です。我が国に、そのような犯罪行為が蔓延してきた背景からお話しましょう。
⑤電話等を利用した詐欺(俺々詐欺)~駄目もと請求商法
電話や郵便を利用した詐欺として、「駄目もと商法」というようなものがありました。 これは相手方の姿が全く見えないという特徴があります。(前話の「送りつけ商法」はある程度会社事務所は明らかにしている場合があります。売買契約をしているという口実で代金を請求しますので、犯罪にまで至る場合が少ないので、ある程度身元を明らかにしています。)
「駄目もと商法」というのは、駄目でもともという意味で、次のような方法で詐欺をしてきます。
- 若い人をターゲットにして、「インターネットのサイト接続代金の債権を買い取りました。サイトに接続した利用代金がまだ未納のままです。明日までに、2万円を振り込んでください。振り込まない場合には、職場や自宅に直接に取り立てに伺います。」とか、「裁判で強制執行します。」などと架空の請求をはがき等でしてくるものです。
インターネットを使用している人は、どこか変なサイトに間違って接続したかなあという思いとか、人には言えない恥ずかしいサイトに接続したことが公になるのは嫌だなあという思いから、2万円くらいならいいかと思って払ってしまいます。
これは皆が皆払ってくるものではないんですね。インターネットに詳しい人は全くの虚偽の請求だと思いますし、インターネットを利用していない人は全く払うことは考えないでしょう。自分で思い当たるような人だけが払ってくるのですが、請求者は、それほど費用をかけないで請求しているのですから、払ってくれる人が多ければ多いだけ儲かるだけです(1枚のはがき代だけで2万円入るのですから)。はがきを送った人から全部振込がなくても、数人から振込があれば大儲けになるのです。必ずしも全員からもらう必要はなく、もともと駄目な人(詐欺にひっかからない人)もいることを予定していることから、「駄目もと商法」と言います。
これは、詐欺の刑事犯罪ですから、電話をかけてきたり、メールや郵便を送りつけてきたりして、脅し文句をいうだけで、自分の素性は全く明らかにしないのです。これに払うと相手の素性も住所も分かりませんので、後で取り戻すことは全くできません。相手が誰か特定できないからです。幽霊みたいな輩たちです。
- これと同じような高齢者をターゲットにしたのが、俺々詐欺に始まる「振り込め詐欺」です。
ある日、突然電話で「もしもし、おばあちゃん。俺だけど。今、車で交通事故を起こして相手方が怪我していて、示談しないと警察に連れて行かれてしまう・・・。」と孫のふりをして、示談金を高齢者に振り込ませる詐欺のことです。
数年前「よしもとお笑いExpoイン宮崎」の大阪吉本漫才を家族で観に行ったときに、東京ダイナマイトかアップダウンという漫才師が「俺々詐欺」のネタで漫才をやっていました。 ~~「オレオレ」っていう電話がかかってきたら、こちらも「オレオレ」って答えるんだって。普通は、電話先で「もしもし」で始まって、こちらも「もしもし」って答えるんだから、相手が「オレオレ」って言えば、こちらも「オレオレ」って答えるのが正しいとかなんとか言ってました。更に、「おじいちゃん?」って聞いてくれば、「森に芝刈りに」と答え、「おばあちゃん?」って相手が聞いてくれば、「川に洗濯に」って答えればいいそうですよ(笑い話として)。~~
- このような振込め詐欺は、様々なパターンがあります。
- * 交通事故・示談や裁判費用を装うパターン(孫・警察官・弁護士を語る)
- * 定期交付金の振込み手続の代行を装うパターン(市役所職員を語る)
- * 税金の還付手続を装うパターン(税務署職員を語る)
- * 浮気の代償を装うパターン(相手方の男・暴力団・弁護士を語る)
- * 借金の債権譲渡を装うパターン(債権回収会社・債権回収機構を語る)
- * 借金返済の保証貸付けを装うパターン(金融会社や保証会社を語る)
これらの詐欺集団は組織的に動いています。携帯電話を用意する人間、個人情報名簿を用意する人間、電話を担当して請求する人間、振り込まれたお金をすぐに引き出しに行く人間、他人名義の預金通帳を用意する人間などが、まるで正当な仕事をしているみたいな感覚で詐欺をしています。
警察の捜査で何人かが捕まって刑事裁判になって、弁護人として弁護する場合もありますが、彼らは「騙すのが悪いというより、騙される人間がうじゃうじゃいることが途中で楽しくなる。」という異常な感覚でやっているのですから、弁護をしていて愕然とします。警察で逮捕してくれない限り、騙されて振込んだ大金は戻って来ないのがほとんどです。
法律の方も、この様な犯罪を防止するために、自分の預金通帳を他人に貸したり売ったりする人も犯罪として処罰する法律(本人確認法、又は、犯罪による収益の移転防止に関する法律)を作りましたし、犯罪に使用されている預金口座を凍結する制度も作り、口座に残った被害金を被害者に分配する制度(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)も作りましたが、犯罪者側が、振り込ませたらすぐに引き出すということを組織的にしていますので、この制度でも、あまり返金されることはないようです。
(次号から:対策についてお話します。)
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ⑥」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<高齢者をターゲットにした悪徳商法に対する解決策や対策>
今回から、高齢者をターゲットにした悪徳商法に対する解決策や対策について、お話していきましょう。
- 生活上の心構え
「高齢者の生活の三大不安は、「お金」「健康」「孤独」であり、「お金の不安」は、手軽にお金が増えるというようなマルチ商法や利殖商法に騙される素地を作っており、「健康の不安」が健康布団や健康薬品等の訪問販売に騙される素地を作っており、「孤独の不安」は、次々商法や催眠商法に騙される素地を作っている」と、このシリーズでお話ししたことがあります。
まずは、次のように考えましょう。「自分の不安は、自分だけの不安ではなく、他の人も同じ不安を持っています。自分だけで不安解消するのではなく、みんなの力で不安を解消していきましょう。遠慮は要らないのです。」・・・このことをしっかり認識しておく必要があります。その上で、一番大切なことは、高齢者が孤独にならないことです。誰か信頼できる近所の方や身内の方(当然、公的な立場にある民生委員の方々も)に、何でも気軽に話せるような生活環境を作っておくこと、高齢者の周りの人はそのような生活環境を作ってあげることが第一です。
- 「財布を守る」秘訣
消費者生活センターで、悪徳商法から高齢者を守るキャッチフレーズが出されています。
「さいふをまもる」という次のようなキャッチフレーズです。- 「さ」誘い文句にのせられない。
- 「い」家の戸、財布にも鍵かけて
- 「ふ」不審な人には戸を開けない。
- 「を」お断りをいたしましょう。
- 「ま」まずは、家族や消費者生活センターに相談し
- 「も」もしもの時に備えて成年後見
- 「る」留守番でも一人暮らしでも大丈夫。
このキャッチフレーズを紙に書いて、玄関ドアやインターホン受話器前の壁などに、貼っておいて、常に意識する訓練をしておきましょう。
- もうひとつの対策の工夫
悪徳商法をしてくる輩(やから)は、「悪人」であり、昔話の「桃太郎」で言えば「鬼」です。悪徳商法を撃退することは、ちょうど「桃太郎の鬼退治」みたいなものです。そこで、私なりに「桃太郎方式撃退理論」を考えてみました。
悪徳商法の輩を退治するには、桃太郎と同じように三匹の味方、三匹の家来が必要だと思います。桃太郎は、犬、雉(キジ)、猿の三匹の家来を連れて鬼退治に行きました。ところで、なぜ、牛やクマやライオンではなくて、「犬、雉(キジ)、猿」の三匹だったのでしょう?
実は、これには、中国儒教や風水学の考えが生かされているようで、「犬」は「仁」(おもいやり、誠実、)の意味があり、「雉(キジ)」は「勇」(勇気、正義)の意味があり、「猿」は「智」(知恵、知識)の意味があるとされ、悪を倒すには、「思いやり」と「勇気」と「知恵」があれば倒せるという教えを表しているという解釈があります。
そこで、高齢者、特に一人暮らしの高齢者には、次のような意味での「犬、雉(キジ)、猿」の三匹の家来を持つことをお勧めします。
(1)犬【忠誠・誠実】 ⇒ 日ごろから、近所の人や民生委員などお世話をしてくれる人と仲良くしておく。
(2)雉(キジ)【勇気・正義】 ⇒ 悪い人には泣き寝入りしない。嫌なものははっきり断わる勇気を持つ。
(3)猿【知恵・知識】 ⇒ 色々なことを知るように努めて知識を持ちましょう。弁護士 などの専門家へ相談する。
これで、あなたも、立派な「桃太郎」になれるはずです。
そこで、次回は、「桃太郎式撃退理論」の各論(具体的撃退方法)として、「猿(智恵)」のお供としての悪徳商法対策の具体的方法をお話していくことにしましょう。
以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ⑦」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<高齢者をターゲットにした悪徳商法に対する解決策や対策>
今回は、先月の「桃太郎式撃退理論」の各論として、「猿(智恵)」としての悪徳商法対策の具体的方法をお話しましょう。
基本的な対処方法としては、
〈ⅰ〉予防方法(未然防禦 みぜんほうぎょ)~「契約をしない方法」と、
〈ⅱ〉事後対処方法~契約をした場合の取り戻し方法」~がありますが、契約をした後の事後対処方法は、相手方の所在がわからないか、会社の実態が全く不明という場合がほとんどですので、被害金を取戻すには相当な困難が伴います。
まずは、予防方法(未然防禦)~「契約をしない方法」を身に付けておいたほうがよいと思います。
1.自宅訪問販売に対する対処方法
まず、高齢者の一人暮らしでの訪問販売への対応手段としては、鍵をかけて訪問販売を断わる・家に入れないということが第一なのですが、日常生活の中で全く第三者に対応しないというのも寂しい限りですから、つい対応してしまいます。
仮に、訪問販売者と対応しても、次のように意識しておく必要があります。
ⅰ>訪問販売者か否かの確認と判断基準
特定商取引法3条に関する通達では、まず突然に居宅を訪問する場合には、「玄関口から」インターホン等で冒頭に「事業者名」「勧誘目的であること」「商品名」を告げなければならないことになっています。予め、電話で訪問の約束を取り付ける場合でも、電話口で「事業者名」「勧誘目的であること」「商品名」を告げなければならないことになっています。無関係な話題で居宅に入り込んで売り込みをした場合には、特定商取引法3条の明示義務違反となり、別途、住居侵入罪になる可能性もありますので、無関係な話で入り込んで、その後に、商品販売の話をした人には、「あなたは法律違反だ!」と告げることもできます。
訪問販売者か否かの区別は、訪問者が名乗るかどうかで区別できる建前になっていますが、悪徳業者ほど名乗らずに、関係のない話で家に入り込んで、家に入ってから突然売りつけようとしますので、結局は、訪問販売だと告げない人も知らない他人は家には立ち入らせないということが一番賢明な方法だろうと思います。
ⅱ>訪問販売者と知らずに中に入れてしまった場合の対処方法
こういう場面は、無関係な話で入り込んで、その後に、商品販売の話をしてきた場合ですから、まずは、「貴方のやり方は、法律違反ですね。」と強く言って、帰ってもらうこともできるでしょう。
法律違反かどうかは、販売員も研修を受けたりして法律の聞きかじりをしていますので、それだけでは太刀打ちできないかもしれません。そういう場合には「息子に相談してからにします。」「相談にのってくれる友達に話してみてからにします。」「民生員の人に相談することになっていますので」と他人の意見を聞いてからでないと契約しないという態度を示すことがいいと思います。
「印鑑がないので」という拒否の仕方では、クレジット契約などは三文判でも通用していますので、販売者側は「サインだけでもいいんですよ。印鑑は、私のほうで印鑑屋さんで買い求めて押しておきます。」な~んて言ってくるので、あまり有効ではありません。
ⅲ>契約をしたくない場合
商品に興味があって家に入れてしまったが、値段や商品の種類が気に入らないので、断わってもしつこく勧めてくる場合が、対処が難しいと考えている方も多いと思いますが、相手方訪問販売者が、法律違反をしていないとしても、実は法律違反をしていることになります。
特定商取引法6条3項で、契約を締結させるために人を威迫させたり困惑させてはならないとされています。また、省令7条1号では執拗に勧誘を継続する行為については「迷惑を覚えさせる行為」として違法としていますし、帰って欲しいと退去を求めたのに帰らない場合には刑法130条の不退去罪(懲役3年以下、罰金10万円以下)になりますので、「これ以上は、迷惑なので帰ってください。」とはっきり言えば、相手方販売者のしつこく勧めてくる行為は違法な行為になりますので、積極的にご自分の考えを声に出していくことが肝心なのです。更に、「これ以上は警察に連絡します。」「消費者センターに連絡します。」という言葉を言っても大丈夫です。
要は、「猿」の知恵としても、「雉」の勇気を持って、「言うべきことは言う。」ことが撃退法になるわけです。
2.電話・ハガキでの振り込め詐欺に対する対処方法
これらへの対処法は、「一人での対応・即断はしない。誰かに相談を!」に尽きます。
振り込め詐欺の電話やハガキなどへの対策は、目の前に相手方がいる訳ではありませんので、本当は、時間的に余裕のある話なのですが、「今すぐでないと間に合わない。」、「公表されたり、裁判になったりして公になると今の段階で早い解決をするしかない。」という“急がせ文句”必ず付いてきます。自分にも余裕がないほど急がなくてはならないお金の支払いなんて、本当は全くないのです。仮にあるとしても、それはそもそも間に合わない問題にしかすぎません。
そこで、「今すぐでないと間に合わないお金の支払いはしない!」と肝に銘じておく必要があります。
そうしますと自ずから自分で考える時間ができるわけですから、信頼できる家族・知人・ヘルパーさんに話して相談する時間もあります。是非、自分以外の誰かに相談した上で、出すべきお金であれば出すという判断をすることを心がけておくべきです。
相談相手がいないときは、民生委員さんでも、交番でも、相談電話かけていいんですよ。 誰かに相談すれば、「何か変だ。おかしい。」という返事をくれるはずです。一人では対応・即断しないことです。電話やハガキの場合でも、消費者センターの指導格言「さいふをまもる」は使えますので、紙に書いて電話などに貼っておいてください。
<さいふをまもる>
さ・・・誘い文句にのせられないで
い・・・家の戸、財布にしっかり鍵かけて
ふ・・・不審な人には注意して
を・・・お断り上手になりましょう
ま・・・まずは、家族や消費生活センターに相談
も・・・もしもの時に備えて、成年後見制度を利用
る・・・留守番、一人暮らしもこれで安心
次回は、事後対策・事後解決策を予定します。
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ⑧」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<事後的対策と解決策について>
高齢者が訪問販売や振り込め詐欺等の被害にあった場合、事後的に対応する方法もあります。今回は「被害に遭った場合の事後的対策と解決策」についてお話しましょう。
1.高齢者が訪問販売や振り込め詐欺等の被害にあった場合には、泣き寝入りはせずに、悪い人間は許さないという強い意思で法的手続をされることが必要だと思います。法的手続きになりますので、まずは、消費者(生活)センター・弁護士会・警察などへの相談窓口に相談してください。
*宮崎県弁護士会・☎0985-22-2466
*宮崎県消費生活センター 宮 崎 ☎0985-25-0999
〃 延岡支所 ☎0982-31-0999
〃 都城支所 ☎0986-24-0999
*宮崎県警 「悪質商法110番」相談窓口 ☎0985-22-8080
2.事後的対応方法の概要だけを簡単にお話ししておきます。 訪問販売で契約した場合には、
① まず、クーリング・オフで契約解消ができますので、この通知をしてください。クーリング・オフのクーリングはクール(Cool 頭を冷やす)の意味で、押しかけられて頭がパニック状態になって契約したものを、頭をクールにしてみたら、要らない商品だったので契約をオフにする(契約をやめる)という制度です。
普通、契約を辞めたい場合には、正当な理由や相手方の解約理由が必要なのですが、このクーリング・オフは、8日間内の契約解除であればよいだけで、契約を辞める理由は全くいりません。ハガキや封書で、とにかく文書で相手方販売会社へ「契約は辞めます。」「クーリング・オフをします。」と書いて送ればいいだけです。典型書式を下に書いていますので、参考にしてください。
しかし、大切なことは、その文書の控えをちゃんと残しておくか、又ははっきりした証拠として残すために、内容証明郵便か書留郵便にして通知することです。これは、後で争いになったときに、「8日以内の通知だったか」「本当に通知したのか」を証明する必要があるからです。
<クーリング・オフの通知文書の書き方の例> ※ハガキで出す場合(必ず簡易書留にして、コピーをとっておく)
| あて先 〒○○○ ▲県△市××××番地 有限会社○○○(××課) 行き |
契約の解除通知契 約 の日 平成○年○月○日 買ったもの ×××××××××××××× この契約の申し込みを撤回します(契約を解除します)ので、通知します。 支払ったお金を返していただき、買った商品を引き取ってください。 平成○○年○○月○○日 住 所 氏 名 印 |
② それでは、8日以内に通知できなかった場合には泣き寝入りしないといけないのでしょうか?8日の起算日は有効な契約書が交付されたときからなのですが、その契約書を細かくチェックすると有効要件を具備していない無効な契約書であり、8日間の起算が始まっていない場合もあります。だから、まだ8日が経過していない事も多くあります。
次に、法的な8日が経過した後でも、消費者契約法違反や民法の詐欺・脅迫で契約自体を取り消したり無効にする方法もあります。ですから、必ず弁護士や消費者生活センターに相談に行かれることをお勧めします。
③ 強引な訪問販売や悪質・高額な販売を受けたときには、刑事上の詐欺罪や脅迫罪になります。振り込め詐欺などは、警察に被害届出をしてください。警察が逮捕してくれれば、いくらか戻ってくる可能性もでてきます。
④ 最後は、行政相談として、その業者を県の消費者生活センターなどに訴え出て、行政処分をしてもらう方法もあります。
次回はこのシリーズの最終回の予定です。一人暮らしの高齢者が自分の財産を守る制度の利用をお話する予定です。 以上
高齢者と法律 「トラブル発生の未然防止策 ⑨」
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
<トラブル発生の未然防止のための成年後見制度・弁護人顧問制度>
今回は、このシリーズの最終回として、高齢者が、自分の情報不足や判断力不足を悪用されて被害に遭わないように、事前に、情報不足や判断力不足を補ってくれる制度のお話をしましょう。
- まず、独居高齢者だけでなく、同居生活を送っていても、日本の孤独化・家庭関係の希薄化の生活関係からして、様々な法的トラブルが当然起こる状況にあります。
親のサラ金借金・学生である子供のサラ金借金・男女付き合いでの妊娠責任・パソコンサイト接続での出会い系料金・保険なし車の運転による交通事故・会社リストラの突然解雇など様々な法的トラブルが一般の日常的な家庭でも起こってきています。
このような個別的トラブルが起きやすくなった背景には、平成4~5年までのバブル経済での新自由主義経済の流れと平成10年くらいからの小泉政権下での規制緩和政策・自己責任世界の実現という日本らしくない政策があります。要は、信用と基盤のある会社に許可を出して行政が規制しながら営業させていたものを、規制をはずしてどこの誰でもやっていいということにしてしまったわけです。
どこの誰でもいいのであれば、どんな商品が売られるかも事前規制できず、どんな商売の仕方でなされるかも規制できず、要は、「国民(消費者個々人)が、自分の判断でいい商品・いい会社を判断しなさい。」という社会なんですね。そうすると、判断する情報や知識のない人は、言われたままの商品を買い、損をしてしまうのではないかという危険があるのですが、それは「自分が判断したんだから、自己責任です。」というわけです。
老後の介護という視点だけを取って説明しますと、従来は、市町村が国のお金で(予算で)老人の介護施設を作って、介護・保護の必要な老人には、措置として、必要な施設への入所と費用負担をしてくれていました。それに対して、平成12年4月から導入された介護保険制度は、自分の介護は自分の介護保険に保険料として支払っておいて、自分の意思で自由に介護施設と介護契約して代金を払ってくださいという制度になり、自由に判断できない人、自由に契約できない人はどうするんだという問題になりました。この点でも、判断する情報や知識のない人は、言われたままの介護契約を結ぶか、介護を受けないままか、いずれにしても、損をしてしまうのではないかという危険があるわけです。 そこで、法律上、十分に判断できない高齢者のために、弁護士や親せきなどの判断能力の十分な人が補助するという後見人制度を充実させました。
- 成年後見人制度とは?
判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。ドイツでは “世話法” と呼ばれていますが、日本では、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって平成12年(2000年)4月から “成年後見人制度” が設けられました。
簡単に言えば、高齢者となって、又は病気となって、判断力が落ちたので、親戚の人や弁護士や司法書士さんなどに、相談しながら決めたいときに、家庭裁判所に申し立てて、親戚の人や弁護士や司法書士さんなどを “後見人” (他に、保佐人、補助人も選べます)。に選任してもらうことができます。
弁護士や司法書士の場合には、仕事としてやっていますので、有料(月3万円~5万円)になります。
- まだ健康なうちに、任意成年後見契約制度で弁護士利用を!
家庭裁判所に申し立てる成年後見は “法定後見” と言って、自分が判断能力不十分とならないと認められないのですが、まだ、健康なうちでも、後見人を選んで後見して欲しいということもあると思います。その場合には、 “任意後見” 契約を公正人役場で公正証書で取り交わすことで、弁護士などを任意後見人とすることもできます。(かつて、私も86歳のおばあちゃんを任意後見して財産管理をさせてもらっていた時期がありました。)
このような弁護士との任意後見契約は弁護士との契約以外に公証人役場での公正証書手続が必要ですが、これは、やはり弁護士でも悪いことをしてしまう者がいるので、任意後見契約は後見人登録をして公にしておいたほうがいいだろうという考えに基づくものです。そのための手続の負担に面倒な点(弁護士費用以外に公正証書作成費用がかかる、公証人役場に行かないといけない等)があります。
- まだ健康なうちに、弁護士顧問契約(ホームロイヤー)で弁護士利用を!
信頼できる弁護士がいれば、財産管理は任せないでも、「必要なときに相談にのってくれたり、電話で助言してくれたりするだけでも十分だ。」と思う人は、その弁護士と “個人顧問弁護士契約” を結べばいいわけです。会社や事業ではなく、個人としての顧問弁護士契約は、日本ではあまり多く利用されていませんが、今後は増えていくだろうと思います。今のところ、事業をしていない個人の顧問契約の場合には、月5千円~2万円程度の顧問報酬で契約していますので、訪問販売や個人トラブル、諸手続で分からないことをいつでも聞ける個人顧問弁護士がいるということで、弁護士を利用していただくことが便利ではないかと思います。いつも行く病院のお医者さんや往診してくれるお医者さんを「ホームドクター」と言いますが、弁護士の場合も「ホームリーガル」「ホームロイヤー」として駆けつけてくれる、相談相手になってくれる弁護士をつける時代になっているのかも知れません。弁護士個人顧問契約をしておられると、将来の子供たちの財産争いを防止する意味での「遺言書」の作成相談や遺言書の保管もしてもらえるメリットもあります。
私の事務所も、私以外に弁護士スタッフ1名、事務スタッフ3名がいますので、個人顧問弁護士契約はどしどし申し付けていただいても構いませんよという宣伝を最後にしておきましょう。
以上
TEL:0985-27-7711 FAX:0985-20-1271
Copyright© 宮崎県町村会 All rights reserved.
本ホームページに掲載されている文章、写真、その他のすべての情報の著作権は、宮崎県町村会が保有しています。