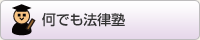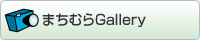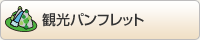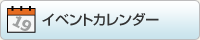何でも法律塾

掲載された文章・画像等の無断転載を禁止します。著作権は宮崎県町村会またはその情報提供者に属します。
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ①
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
前置き : 昨今、「法教育」制度の運用が始まろうとしていて、小中高学校において法律的な考え方を教育する方法が検討されています。小学生に対しては、事実関係の分かりやすい御伽噺を題材にした話が工夫されたりしています。もう7~8年前に「御伽噺を法律的に考えるとどうなるか」という出版活動をしたことがあります。年末年始のバタバタの時期に皆さんに一息付いてもらう題材として、その例を、挙げていきます。適当に楽しんでみてください。
【 桃 太 郎 】
- (質 問)
-
鬼ケ島の鬼が、頭に包帯をし、松葉杖を突きながら、痛々しい姿で「桃太郎にこっぴどくやられました。仲間もたくさん死んだ。財宝も全部持って行かれた。やり方がひどすぎる。桃太郎が英雄のままでは納得がいかない。これは犯罪じゃないでしょうか。桃太郎を刑事告訴したい。う、うううわ~ん。」と泣きながら法律相談にきました。
桃太郎やキジ・猿・犬は刑事犯罪者なのでしょうか?(それぞれ「人間」と想定して検討します。)
- <回 答>
-
1. 法律では「人間」以外は「物」と見ますので、「鬼ケ島の鬼」が「人」か「物」かという根本的な疑問がありますが、鬼も「生命を持ち人間の悪性のみを凝縮した人間」という意味合いで理解し、「人」であるという前提で、桃太郎やキジ・猿・犬の行為(鬼の征伐)が刑事犯罪となるのかどうかを検討してみましょう。
2. 鬼を人間と仮定した場合、鬼ケ島での鬼の財宝は、鬼が所有・占有する「財物」となりますが、財宝が「村の人々から盗んだ物」であっても、鬼の所有・占有が法的に認められ、刑事処罰の被害品として法律は保護するのかどうかが、まず問題になります。強盗罪や窃盗罪の保護法益の問題です。ここには、① 盗まれた本人が取り戻す場合と、② 盗んだ物を更に第三者が盗む場合との2つの場面が検討される必要がありますが、② の場合には、「盗まれた物を更に盗むことは窃盗罪等になる。」ということで争いはありません。問題は①の場合と考えられるかどうかですが、桃太郎が村の人々の代理として盗まれた物を取り返しに行ったという面を考えれば、①の場合として考えることになります。
3. 自分の物を盗まれたので、直ぐに犯人を追いかけて取り戻すことは許されるかという問題は、刑法上、「自力救済」「自救行為」として、犯罪の成立要件である「違法性」を阻却されることとなり許されています。しかし、それも、犯人が盗んで間もない状態(時間的同一機会・場所的同一性)であり、その場で警察等の国家的救済手続を取る暇のない緊急状態であること(緊急性)、取り返し方法が社会的に相当な手段でなされること(手段の相当性)が必要です。そこで、桃太郎の場合の鬼の財宝について、「自力救済」としての「同一機会性」「緊急性」「手段の相当性」の要件を満たしているかどうかが問題となります。鬼の財宝は今盗んできたようなものではなく、昔から盗み続けてきたものであり、犯罪現場との同一性を認めることは困難であります。また、桃太郎は、キジ・猿・犬にキビ団子を渡して奪取兵力の準備までしており、今鬼を征伐しないと警察を頼む余裕がないというような場面でもありません。手段も、財宝を奪い返すことだけでなく、金棒も持たないで酒盛りをしていた鬼たちを一方的に襲撃していますので、手段の相当性を逸脱していることとなります。そうしますと、桃太郎たちの行為は、「自力救済」とは認められませんので、違法性のある行為と言わざるを得ません。
4. また、鬼ケ島の鬼の財宝は、そもそも村人らから略奪してきたものであり、それを盗み返しても鬼たちには被害はなく、窃盗罪や強盗罪は成立しないのではないかという疑問があると思いますが、財産犯罪の被害法益(保護法益)は、正当な所有権・占有権だけでなく、「平穏な占有」で足りるとするのが最近の刑法学会の多くの見解です。刑法242条には「自己の所有物であっても他人が占有するものであるときは他人の財物とみなす」とする規定も存在します。盗んできた物でも一旦争いのない状態で物を管理している状態があれば、違法な行為で獲得した物であっても、それを盗むと窃盗罪等になるという結論になります。従って、この点からも、鬼ケ島の鬼の財宝を個人的に奪い返すことはできなく、法律上は、民事強制執行等の法的手続きで返還請求するか、鬼の同意を得て返還を受けないといけないということになります。
5. 以上のことから、桃太郎は、鬼を殺したり傷つけたりして財宝を盗んだということになりますので、刑法240条の強盗致死罪(死刑又は無期懲役)が成立することになります。なお、キジ・猿・犬はその共犯(共同正犯・刑法60条)となり、おばあさんやおじいさんも少なくとも、その幇助犯(犯行をしやすくするために援助した=キビ団子を作って送り出した)として処罰されることになるでしょう。
6. 最期に、桃太郎は、警察や裁判制度のない時代のお話ですので、桃太郎が警察と同じような役割を担ったんだという面は充分に考えてやる必要があります。国家に正義を守る機構がない場合には「桃太郎」や「桃太郎侍」が必要だった時代もあったのでしょう。そのことは忘れて、形式的な法律適用をすることは極力避けなければいけないと思いますが、形式的に法律問題を考えた場合の一つの解釈例であるとお考えいただければ幸いです。
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ②‐1
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
まずは、皆さん、さわやかに新年をお迎えになられたことと存じます。今年もよろしくお願い申し上げます。
新年最初に、若い男女の優しさを感じさせるお話を法律的に紐解いてみましょう。
さて、「美女」と「野獣」は二人一緒にお正月を迎えられたのでしょうか?
【美 女 と 野 獣】(前編)
- (質 問)
-
「美女と野獣」のお話は、フランスの昔話でデイズニー映画などでも有名ですが、美女は父親がバラの花1本を野獣の屋敷から取って来たために、脅されて娘の美女を代わりに差し出せと言われて、醜い野獣と一緒に生活させられます。しかし、野獣が優しい人であることが分かり始めています。美女は夫の野獣とのんびりとお正月を迎えたいと思っているのですが、美女は最近、警察が、父親や夫である野獣を逮捕するといううわさを聞いて心配でたまりません。
父親や夫の野獣は犯罪者なのでしょうか。教えてください。
- <回 答>
-
1.野獣と法律
野獣とは、「山野に住み獰猛で人に慣れていない獣」「野生の獣」であり、法律上は「物」に該当するもので、「人」には該当しません。法律は人と人との関係を規律するもので、「物」は権利の主体にはなれないとされています。しかし、「美女と野獣」での野獣は、本来は王子様でありそれが魔法で野獣に変えられていますので、「野獣」=「人」と考えて法律問題を考えていきます。
2.父親とバラ1本の窃盗?
まず、美女の父親の問題を考えましょう。「バラの花を一本取って」という行為は、刑法235条の窃盗罪となります。刑法235条には「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし10年以下の懲役に処する」との規定があります。但し、刑法理論上は、わずかな価値しかない財物と取った場合でも犯罪が成立するのかという問題があります。犯罪が成立するには、① 構成要件該当性(法律の定めた犯罪の形態に該当すること) ② 違法性(法律を初めとする社会的規範に反していること) ③ 有責性(規範を意識して自分の責任を認識できること)の3つの要件が必要です。②の違法性の判断で、犯罪とするには処罰するほどの大きな違法性が必要ではないか、わずかな違法の場合には「可罰的違法性」がないとし犯罪成立に必要な違法性はないとする考え方(可罰的違法性論)があります。「価格一厘にあたる葉煙草」を政府に納入しなかった煙草専売法違反事件で無罪とした判例(明治43年10月11日大審院判例:一厘事件)がありますが、裁判例のほとんどは経済的価値がわずかな場合でも犯罪を成立させていますので、父親には窃盗罪が成立します。
3.野獣のしたことは違法なの?
次に、野獣がした行為や要求が、法律に違反しているかどうかの問題を考えてみましょう。
(1) まず、窃盗犯の現場を見つけた被害者が犯人を捕まえることが許されるでしょうか。これは当然許されています。刑事訴訟法213条は「現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」としています。但し、私人による逮捕の場合には、直ちに検察官か警察官に引渡さなくてはなりません(刑事訴訟法214条)。この手続を無視して逮捕したままの状態を長く続けると、刑法220条の逮捕監禁罪が成立しますが、野獣はすぐ美女の見返りを要求して父親を帰していますので、刑法220条の逮捕監禁罪とはならないでしょう。
(2) 野獣は、美女の父親に対して逆に損害賠償を請求することができました。美女の父親の「バラの花を一本取って」という行為は、民事上の不法行為となります。民法709条は「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は之によりて生じたる損害を賠償する責に任ず」と定めています。父親は故意に他人である野獣(?)の所有するバラの花の所有権を侵害して盗んだことになりますので、損害賠償義務を負います。
しかし、野獣は損害賠償というより、「娘を代わりに差し出せ」と要求している点が非常に問題となります。民事上の不法行為責任に関しては、民法417条で「損害賠償は別段の意思表示なきときは金銭を以って定む」とあります。この条文では、損害賠償は金銭でするという金銭賠償の原則が認められているのですが、例外として双方の意思によって金銭以外の方法での賠償もできるような条文になっております。「バラのことを許して欲しければ、お前の娘を連れて来い」という要求をし、父親が弁償方法として「娘を差し出す」弁償方法を真摯な気持ちで了解したとするとその方法は許されるのでしょうか。いわゆる人身売買の方法は今の法律では「公序良俗違反」の意思表示となりその承諾や了解は法律上無効となります(民法90条)。従って、父親が強迫されていた場合でも、仮に強迫ではなく真摯に了解したとしても、金銭賠償以外の方法として「娘を差し出す」ということは有効な損害賠償方法とは認められません。 (なお、「強迫」は民事分野の場合に使用し、「脅迫」は刑事分野の場合に使用する言葉として区別されています。)民事上の強迫で法律行為などをさせ、有効な法律関係で無い場合には、刑法222条の脅迫罪や刑法223条の強要罪となりますが、野獣の行為は「娘を差し出すことを要求した」だけにとどまらず、実際に「娘を差し出させた」という結果が発生していると考えられます。刑法222条の脅迫罪や刑法223条の強要罪にとどまらないと考えるべきです。刑法225条の営利目的等略取誘拐罪が適用されると考えます。刑法225条は「営利・わいせつ又は結婚の目的で人を略取し又は誘拐した者は1年以上10年以下の懲役に処する」と定めています。「略取」は暴行・脅迫を手段として他人を不法に保護生活環境から離脱させて自己の支配内に置くこと、「誘拐」は欺したり誘惑したりする方法を手段として他人を不法に保護生活環境から離脱させて自己の支配内に置くことをいいます。ここでいう「結婚目的」は法律上の結婚ではなくても事実上の結婚・内縁関係であれば足りると解釈されていますので、美女と野獣のお話の場合には、野獣には、刑法225条の営利目的等略取誘拐罪が適用されると考えます。
また、長い間美女を拘束していますので、刑法220条の逮捕監禁罪も別個に成立することになります。
~ 「後編」に続く ~
ところで、「美女と野獣」のお話は、最後はどのようになっていたか覚えていますか?次回、後編では、美女が野獣を助けることができる法理論を考えます。
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ②‐2
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
【美 女 と 野 獣】(後編)
前回、「美女と野獣」のお話では、野獣に対して、刑法犯罪として刑法225条の営利目的等略取誘拐罪、刑法220条の逮捕監禁罪が成立してしまうことをお話しています。美女は、野獣の本当の優しさが分かっています。野獣を刑事犯罪者にはしたくありません。さて、美女が野獣を助ける方法はないか。考えてみましょう。
1.まず、美女は野獣の外見の醜さを超えてその心の優しさを知り、結婚していますし、美女自身が犯罪被害者です。
ところで、犯罪被害者が刑事処罰を望まない場合には法律はどうなっているのでしょうか?「被害者の事後承諾と親告罪」ということで説明しましょう。
(1) 犯罪の成立は、犯罪行為が行なわれた時点において、①構成要件該当性(法律の定めた犯罪の形態に該当すること)②違法性(法律を初めとする社会的規範に反していること)②有責性(規範を意識して自分の責任を認識できること)の3つの要件が存在するかどうかで判断されます。被害者が行為時点で犯罪行為に対して承諾(心からの真意の承諾)がある場合には、違法性が阻却され犯罪が成立しない場合もあります(窃盗罪・器物損壊罪で事前に処分を任されていた場合や出入りを事前に許されていた場合の住居侵入罪等)。犯罪の種類によっては、被害者の承諾があったとしても別の軽い犯罪が成立したり(殺人罪の承諾があれば承諾殺人罪となる等)、犯罪に全く関係ない場合もあります(受託収賄罪等)。
(2) しかし、犯罪が成立する時点での承諾が無く、犯罪が成立した後に承諾した(事後承諾)場合には、その事後承諾は犯罪の成立には影響を与えません。事後承諾は、事件後の示談(犯人と被害者との話合での解決)と同じように、処罰をどのくらいの刑にしたらよいかという「量刑」を裁判所が判断する場合に刑が軽くなる方向で参考にされるだけになります。
(3) 事後承諾に近い問題として「親告罪」があります。これは犯罪の成立要件3つの他に処罰要件として考えられるものです。犯罪が成立しても一定の特殊な犯罪に関しては被害者の親告(告訴)がないと処罰できないとしている制度です。これは、被害者が犯罪で被害を受けながら裁判手続を被害者に無断で進めると更に被害者に被害を与えてしまう可能性のある罪や軽微な犯罪の場合に要求されているものです。
実は、逮捕監禁罪は親告罪ではないのですが、結婚目的略取誘拐罪は親告罪となっています(刑法229条)。被害者本人のプライバシーの保護の要請が強い場面だからです。
従って、この点については、結婚目的略取誘拐罪については、「美女」が告訴をしなければ、「野獣」の逮捕・勾留や裁判手続きには進まないでしょう。また、「美女」が告訴したとしても婚姻を解消した後での告訴でないと告訴の効力はありません(刑法229条但書)ので、「美女」が野獣と離婚しない場合には警察は野獣を犯罪者とすることはできません。警察は美女が告訴しない限り、刑法220条の逮捕監禁罪でしか動かないでしょう。しかも、その逮捕監禁罪についても、美女の事後承諾や許しがあるとすれば、刑事裁判まで手続きしていくような刑事事件としては立件しにくいと思います。仮に、警察が逮捕に動いたとしても、刑事手続は、警察の捜査・逮捕後には検察官に事件送致(勾留)され、検察官が裁判をするかどうかを決定します。裁判する場合を「起訴する」(公訴提起)といいますが、裁判しない場合を「不起訴」処分といいます。不起訴処分の理由として、無罪である場合の「嫌疑なし」、無罪か有罪かどうか不明の場合の「嫌疑不十分」、有罪であるが起訴する必要がない場合の「起訴猶予」などがあります。本件では「美女」の許し(事後承諾)があったとしても、逮捕監禁罪が成立しそうですが、それについても「起訴猶予」の判断がなされ釈放される可能性が高いと思われます。
(4) 父親の窃盗罪についても、被害が軽微であり、野獣が事後でも許しているとすれば刑事事件として警察が取り上げることはないでしょう。
2.最期に
美女は心配しないで、野獣を積極的に評価する話を警察にすればいいのです。そうすれば優しい夫と幸せに暮らせることは間違いないと思います。
なお、「美女と野獣」の文学的価値を下げないために、ひと言付加します。「突然に外見の醜い野獣と一緒に暮らさなくてはならなくなった場合に、あなたはその野獣の外見に囚われずにその心の優しさを感じ取り、外見上の恐怖感や嫌悪感に打ち勝つことができるでしょうか。」
このような心の問題を、美女と野獣の物語はあなたに突きつけています。あなたの心が試されている物語です。「美女」のように心の優しさを本当に感じられる素敵な女性や「野獣」のような心優しい男性が多くなるといいですね。そうなれば、法律や刑罰はほとんど必要なくなるのかもしれません。
以 上
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ③
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
【花 咲 か じ い さ ん】
- (質 問)
意地悪じいさんが、花咲じいさんを妬んで、弁護士の法律相談に来ました。相談内容は次のような相談でした。「花咲じいさんのお話では、私も悪かったと反省してはいるんですが、良いおじいいさん(花咲じいさん)のほうだって、子犬を拾ってきて飼ったり、土から出てきた財宝などを手に入れたりしていますが、このように勝手に自分の物にすることは許されるのでしょうか。」
さて、意地悪じいさんの相談に応じてみましょう。
- <回 答>
弁護士の法律相談は、先に善悪を決めてどちらかに有利になるように相談に乗ることはしません。事実が法律的にどうなるかを検討した上で、その行動が良かったのか悪かったのかを判断します。
そこで、意地悪じいさんの相談も聞いてあげることにしました。
次の内容が弁護士の考え方(法律的な考え方)になります。
-
1.子犬を拾ってきたこと
おじいさんが、野生のタヌキなど明らかに「無主物」であるものを捕ってきた場合には、これを先に占有した者がその動物の所有権を取得することになりますから(民法239条)、捕まえた者が、家で飼おうが、売ってしまおうが自由です。このことを「無主物先占」(むしゅぶつせんせん)と言います (そのような動物をペットなどにしている場合もあり得るのですが、民法195条で、「家畜外の動物」であれば、これを占有したときに他人の所有物であると知らずに飼育し続け、1ヶ月が経過しても元の飼い主からの請求を受けなかった場合には、所有権を取得できるものと規定しています)。
① 人の飼い犬と思われる場合
まず、子犬は普通はペットとして飼われているものですから、これを明らかな「無主物」と同じに考えることはできません。首輪などがついている場合は当然として、首輪がなく飼い主が誰であるか分からない場合でも、「遺失物」(人の物であることは分かるが、誰の物かがわからない物)として取り扱うことが必要と思われます。「遺失物」ということは、拾った財布などと同様に扱う必要がある、ということです。
そこで、遺失物法によれば、他人の遺失物を取得した者は、すみやかに遺失物を遺失者に返還するか、警察(交番など)に届け出をしなければなりません。そのうえで、3ヶ月間以内に飼い主が現れなかった場合には、取得した者が所有権を取得することになります(民法240条)。しかし、犬のような生き物の場合に、警察や交番で飼育預かりをしてくれるような体制にはなっていないようです。遺失物法9条、10条で、管理しにくい物や管理費用のかかる物の場合には、二週間以内にその遺失者が判明しない場合には、売却したり廃棄したりすることができるようになっていますので、犬・猫の場合には、遺失物法10条三号により、保健所に送られることになるようです。
花咲かじいさんは、警察への届け出をせずに、勝手に子犬を自分の飼い犬として育てていますが、もし、もとの飼い主が現れた場合には、犬をその飼い主に返還しなくてはなりませんし、犬が管理不十分で死んでしまったような場合には、飼い主から損害賠償を請求される可能性もあります。
それどころか、勝手に、これを自分の犬として飼ってしまうと、占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料、という刑罰に処せられる可能性もあります。
② 捨て犬である場合
この子犬が捨て犬などの場合には、もとの所有者(飼い主)は子犬の所有権を放棄したといえるので、無主物と同じに扱って、花咲かじいさんが子犬の所有権を取得したと考えることも出来るでしょう。無主物先占により新たな所有権が認められるわけです。
③ まとめ
しかし、一般的には、①と②のいずれにせよ、子犬を拾った時点では、もとの飼い主のもとから逃走してきたのか、飼い主が捨てたのか、分からないわけですから、警察に届け出をなすべきだった、といえるでしょう。しかし、動物愛護の強い人は、警察には届けないで、預かったままで飼い主を探してくださいと主張する人も多くいます。そこで、警察に届け出るけれども、警察から了解を得て、拾い主自身で預かってもらって飼うか、動物保護センター等で預かるという方法がいいのかも知れませんね。
2.埋蔵金を持ち帰ったこと
埋蔵金についても、犬の問題と同じ、つまり拾った財布と同じで、遺失物法が適用されます。誰の所有物か分からないわけですから、警察に届け出る必要があります。これをせずに、勝手に使ってしまったりすると、占有離脱物横領罪(刑法254条)で処罰される可能性があります。 仮に警察に届け出ていたとしても、全額がもらえるわけではありません。埋蔵金といっても、誰かのへそくりを隠しただけかもしれませんし、埋めた人とその相続関係が分かれば、相続人がその所有者となります。
遺失物の届け出を受けた警察は、埋蔵金の所有者が誰であるかを調べるために、公告・閲覧・備え付けで公示し、それから6ヶ月以内(埋蔵物の場合)に所有者が分かれば、警察としては埋蔵金の全額をその所有者に返還します。発見した人は、埋蔵金の価格の5パーセントから20パーセントの「報労金」をもらう権利があるだけです(遺失物法7条、28条)。一般的に、「財布を拾ったときに10パーセントもらえる。」と言われているのは、この「報労金」のことです。
しかし、所有者が分からなかった場合でも、全額を花咲かじいさんがもらえるわけではありません。民法241条で、他人の土地から埋蔵物が発見された場合には、その土地の所有者と折半することになっています。
・・・最後に、弁護士は、相談者の意地悪じいさんにも「悪いことをあなたもしているのではないか」と、ちゃんと次のことを付け加えました。・・・
3.意地悪じいさんの行いについて
民法や刑法では、動物も「物」と言うことになりますので、犬を殺したり、臼を焼いたりする行為は、刑法上では器物損壊罪(刑法261条:3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)になり、民法上は不法行為(民法709条)になりますから、意地悪じいさんは花咲かじいさんが受けた損害を賠償する責任が生じます。ただし、子犬に関しては、その金銭的価格が賠償金額となるので、同種の犬を他から飼ってくる場合の価額相当額が損害額となります。また、愛玩動物の場合には、そのような物の価値以外にも、精神的苦痛を受けたとして慰謝料が請求される場合もあります。
だから、この世の中では、意地悪ではなく、お互いに仲良く助け合うことのほうが楽しいはずですよ。これからの高齢化社会ではお年寄りには厳しい社会になるかもしれません。意地悪じいさんも、花咲かじいさんたちと高齢者同士で仲良く一緒に楽しんで生きていってくださいね。もうすぐ、桜の季節でしょ。花咲かじいさんに、桜の花を咲かせてもらって、一緒に花見などしたらいいんじゃないですか。
~ おしまい ~
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ④
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
秋の風情が深まる時季です。秋の月を眺めながら『かぐや姫』の話を思い出してみましょう。
- (相 談)
竹取りのおじいさん、おばあさんは、「かぐや姫は、月の両親らしき人物の使いに無理やりに連れ去られたんだ。」と思っています。かぐや姫は、泣く泣く「本当はおじいさん、おばあさんとずーっと一緒に地球で暮らしていたい。」と話していました。「本当は、地球で一緒に暮らしたいと願っているのですから、どうにかして、かぐや姫を取り戻して欲しい。」と泣きながら、法律相談にやってきました。法律は、どうしてあげることができるのでしょうね。
- <弁護士のさてさて話>
さてさて、これは難問、難しいご相談ですなあ・・・・。
かぐや姫は、まだ、20歳未満の未成年だと思われます。法律的には、未成年として自分の親(月の両親?)の親権に服することになります(民法818条)。おじいさんとおばあさんは、事実上の監護者としてかぐや姫の面倒を看てきただけであり、基本的には法律的な権利は有していません。(しかし、例外的に養子縁組をしているかもしれません。)
したがって、今のままでは、法律上の権利者である親からかぐや姫を取り返す方法は全くない、と言わざるを得ません。 そこで、おじいさん、おばあさんが、かぐや姫を取り返すためには、①親(月の両親)の親権をなくしてしまうこと、②おじいさん・おばあさんが、法的な監護養育権を得ること、という二つのハードルをクリアする必要があります。
- ところで、この月の両親は、生まれたばかりのかぐや姫を竹やぶの中に放置し、そ のままで長期間が経過しています。このような者が、法律上の親であるからといって親権者であるというのは、納得できる話ではありません。民法834条は、親権者に親権濫用あるいは著しい不行跡がある場合には、家庭裁判所は子の親族又は検察官の請求によって、親権を剥奪することが出来ると規定しています。
おじいさん・おばあさんは、法律上の子の親族ではないので、検察官に請求を促し、親から親権を剥奪してもらうことが出来ます。裁判例の中には、7年の長期間にわたって、子どもの養育を怠り、他人任せにしてきた事例について、親権の剥奪を認めたものがあります。
- 次に、親権の剥奪が認められると、その子(かぐや姫)には親権者がいなくなりま すので、「後見」が開始し、家庭裁判所によって後見人が選任されることになります(民法838条以下)。後見人は、原則として、親権を行うものと同一の権利を有する(民法857条)ことになります。
ただし、未成年者の後見人には1名しかなれませんので、おじいさんかおばあさんのどちらかしか後見人にはなれません。
- また、おじいさん・おばあさんが、かぐや姫と養子縁組していれば、養親としての 親権が認められることになりますので、以上の後見人選任手続きをするまでもなく、おじいさん・おばあさん双方に、親権の権限が与えられます。
未成年者の子を養子にするには、実の親の同意がないとできないのですが、未成年者との養子縁組は、未成年者の子どもが15歳以上になれば、実親の同意がなくても、自分の意思で出来ることになっていますから(民法797条)、家庭裁判所の許可(798条)だけを得て、おじいさん・おばあさんとかぐや姫が養子縁組をすることができるのです。この制度は、子供が自分の親を決められる権利を15歳になれば認めてあげる制度であると言ってもいいかも知れません。
- この後見人選任、養子縁組をして、ようやく、おじいさん・おばあさんは、かぐや 姫の引渡しについて法律上の請求をすることが出来ます。
後見人に選任されたおじいさんあるいはおばあさん、あるいは、養親となったおじいさん・おばあさんは、家庭裁判所に「子の引き渡しを求める審判」を申立、同時に「審判前の仮処分」の申立をなしたり、地方裁判所に人身保護法に基づく引き渡し請求をしたりすることが出来ます。
- 最後の結論
しかし、法律上このような請求手続きが出来るようになっても、実際にかぐや姫を取り戻せるかというと、実は大きな問題が残ります。
かぐや姫は、未成年と言っても帝や貴族の男どもとの結婚話が出ているくらいなので、満16歳以上(民法731条-女性は16歳から婚姻可能)と思われます。そうすると、親権といえども、事理弁識能力のある年齢(12~13歳以上)の子どもについては、親権は、その子の自主的判断やその意思を最大限尊重して行使されなくてはならないのですから、かぐや姫の自主的判断やその意思を無視してまで、事を進めることは出来ません。かぐや姫は、おじいさん・おばあさんへの思いは残っていたとしても、自分の意思で月に戻って行ったのですから、おじいさん・おばあさんは、かぐや姫のそのような意思(おじいさん・おばあさんとは別れるのは悲しいけれど、生まれた親の元に帰らざるを得ないという思い)に反してまで、人身保護請求手続きなどで強制的にかぐや姫を取り戻すことも出来ない、と考えるべきでしょう。
仮に、人身保護法上の取り戻し請求に勝訴しても、月の両親やかぐや姫が任意に戻さない(戻らない)場合には、強制的に人間を動かして戻す手続き(差押えや強制執行)は、今の日本の法律制度にはありません。
(参考:「間接強制」といって、引渡判決に従わないと罰金を科しますという命令で間接的に強制する方法があるだけで、罰金さへ払えばかぐや姫を渡さないで済むのかというふうに考える人には、この間接強制方法は何ら効果がありません。)
-
以 上
御伽噺(おとぎばなし)と法律シリーズ ⑤
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
秋も深まり、やがて冬到来の時季がきますね。
「夕鶴」のお話はしんみりした悲しみを漂わせているお話です。
今回は、この「夕鶴」のお話を法律的に考えてみましょう。
- (質 問)
- (回 答)
- 「別れを告げられ飛んで行かれてしまい悲しんだ」という場面を現代の法律に当てはめますと、「離婚」という場面になります。「悲しんだ」ということから、夫の「与ひょう」は離婚したくないという思いを持っていると理解することになるでしょう。
- 離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類があります。
協議離婚とは、夫婦で話し合いをして、離婚届を役所に提出することによってする離婚です。調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停を利用して、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって、離婚の協議をするものです。協議離婚にしろ、調停離婚にしろ、夫婦間で離婚するという合意が整わなければ成立しませんから、本件では、夫側が離婚をかたくなに拒んでいる以上は、これらの方法での離婚の成立は困難だと思われます。そうすると、裁判で離婚出来るかどうかが問題となりますが、民法では離婚原因が定められており、このいずれかに該当しなくては、判決で離婚が認められることはありません(なお、裁判離婚と言っても、「調停前置主義」と言って、裁判の前に調停による話し合いの機会をもうける必要があり、いきなり裁判をすることはできません)。
- 民法が挙げる裁判上の離婚原因は、以下の5つです(民法770条)。
①「配偶者に不貞な行為があったとき」:いわゆる浮気での離婚がこれにあたります。
②「配偶者から悪意で遺棄されたとき」:たとえば、夫婦なのに同居を拒み、生活費なども渡さない場合がこれにあたります。
③「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
④「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
⑤「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」
これらの原因が離婚される側(本件では夫)に存在することが要件となります。
本件では、夫「与ひょう」に浮気・不貞行為もなければ、その他の離婚原因もなく妻「おつう」との夫婦生活は上手くいっていたようですので、離婚が認められるためには「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが問題となってきます。平たく言えば、結婚生活が破綻しており、これ以上一緒に生活していくことが不可能なほどに修復不可能であるか、ということです。夫が妻に度重なる暴力行為をしているような場合には、これに該当しますが、本件は、そのような典型的な事例ではありません。
- 嫁である「おつう」の言い分として考えられるのは、 まず、「夫婦間の約束を破ってしまった夫は、信用できず、これから一緒に暮らしていくことはできない」ということでしょうが、これだけでは離婚は認められないでしょう。というのは、夫婦間においては、夫婦が互いに協力して、その関係を維持・発展させるべきであり、妻が実は鶴だったという秘密がばれたとしても、夫がこれを受け入れて、婚姻生活を続けようと主張するならば、婚姻生活が破綻したとは言えないからです。(現在の法律では、人間と鶴はそもそも結婚できませんが、そのことは考えないことにします。)最初は、秘密がばれて、あるいは秘密を知って、ギクシャクした関係になるかもしれませんが、「そのくらいのことでは、俺の愛は変わらないぜ!」と、夫の方が強く主張すればよいのです。
- 次に、妻の主張として考えられるのは、「夫は自分では働かず、私が身がやつれるほどの苦労をして機(はた)を織って、家計を維持してきた。夫は、私の苦労も知らず、生活費としては十分なお金を稼いだにも関わらず、さらに機(はた)を織らせようとした。もうこんな、自分勝手で、自堕落な男とはやっていけません」ということです。これは、多少、夫の方には分が悪いかもしれません。夫が、自分でも働けるにも関わらず、働きに出ることをせず、無為に生活しているとすれば、妻との信頼関係は崩壊し、婚姻生活が維持できなくなることもあり得ない話ではないからです。
これに対して、夫としては、妻に負担をかけたのは一時的なものであり、夫も定職を持ち働くことを、強くアピールすべきです。裁判の前には必ず調停が開かれますから、それまでに定職を見つけて、収入を確保すべきです。裁判になっても、収入が一定しており、今後の生活の目途が立っているのであれば、離婚が認められない可能性は高いと思われます。(ただ、裁判で離婚が認められないからと言って、妻の気持ちが変わらなければ、その後の結婚生活は円満に戻るわけでもなく苦しいものになりますから、どうしたら妻を納得させられるのかを、よく考えるべきです。)
なお、原則として、有責配偶者(離婚原因を作った方の配偶者)からの離婚請求は認められないので、夫の方としては、「隠し事をしていた妻の方が悪い」という主張をなすことも考えらないわけではないのですが、本件では、「婚姻関係が破綻していないので離婚原因がない」と主張する方が良いと思われます。
- 夫「与ひょう」は、自分の思いを妻「おつう」に告げ、復縁を願う手続をするべきです。再度、ラブレターを出すのもいいでしょうし、求愛行為が必要です。夫「与ひょう」のほうからすべきその後の法的手続としては、家庭裁判所で「夫婦円満調整の調停手続」をすみやかに申立てましょう。
夫である「与ひょう」は、鶴であった「おつう」にあれほど固く“機(はた)織りの現場を見ない”という約束をしたのに、その約束を破ったために、「おつう」から、別れを告げられ飛んで行かれてしまい悲しみます。
「与ひょう」は「おつう」を好きで好きでたまりません。「与ひょう」の「おつう」とは別れたくないという思いを法律的に守れませんか。
以 上
TEL:0985-27-7711 FAX:0985-20-1271
Copyright© 宮崎県町村会 All rights reserved.
本ホームページに掲載されている文章、写真、その他のすべての情報の著作権は、宮崎県町村会が保有しています。