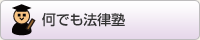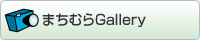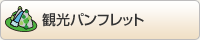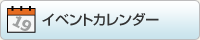何でも法律塾
掲載された文章・画像等の無断転載を禁止します。著作権は宮崎県町村会またはその情報提供者に属します。
公務員の刑事犯罪と法律(~収賄罪逮捕を中心に~):その1
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
山笑い、風光る4月の時期に、新しく公務員生活を始められる方々も多いでしょう。公務員生活は「入り口」としての採用と「出口」としての退職で完結するのですが、公務員としての職務遂行中に様々な誘惑や失敗が起こることもあるでしょう。そういう場面で正当に対処できるために、法律を知って自分の防禦武器としておくことも必要でしょう。そこで、電子化された「何でも法律塾」の1回目として、公務員の地位を全とうしていただくために「公務員の刑事犯罪」を警告的に検討してみたいと思います。
- 公務員の法的扱いの特殊性
公務員採用試験に合格して、公務員の地位を取得すると、民間人と異なり特殊な法的扱いがなされることが多くあります。憲法上は、「公務員は全体の奉仕者」(15条2項)とされ、地方公務員法上は「その意に反して免職・懲戒等をされることはない。」(地公法27条)として身分保障されている反面、職務専念義務・守秘義務・営利事業従事禁止等の職務上の多くの義務負担があり(地公法30条~38条)、更に、刑法上においては、公務員職権濫用罪(刑法193条)や収賄罪(刑法197条)で公務員だけが処罰される犯罪も規定されている立場にあります。特に、全国的に新聞テレビのニュース報道で取り上げられるのは、収賄罪です。そこで、今回は、公務員の収賄犯罪が当該公務員においてどのような経緯を辿って地位を喪失するかを検討してみましょう。 - 公務員の刑事犯罪(収賄罪)と刑事裁判等の法律手続き
(1) 刑法197条1項は「公務員がその職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において請託を受けたときは7年以下の懲役に処する」と規定しており、「公務員になろうとする者」も「公務員であった者」も事前収賄罪・事後収賄罪として処罰される場合がある規定になっています(刑法197条2項、197条の3)。
「五年以下の懲役」というと最低刑は何年なの?と思いますよね。刑法12条に「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は1月以上20年以下とする」と定めてありますので、「5年以下の懲役」とは「最長5年、最短1月の懲役」という意味になります。
ところで、賄賂とは、金銭や品物をもらう以外にも、「接待を無料で受ける」というような経済的利益を受ける場合も含まれますので、職務上関連する業者や関係者と一緒に飲食して奢ってもらうということは、収賄罪になる危険性が高くなります。公務員として、まず、気をつける点です。(2) 収賄罪で公務員が逮捕されますと、次のような人事上の問題が手続されます。
逮捕(勾留)とは、刑事捜査手続において捜査機関に強制的に身柄を拘束されるものであり、逮捕2日間、勾留最大20日間の期間、職場に出勤不能な状態になります。無断欠勤となるのか年休手続をするのかの問題が生じます。捜査段階では、その犯罪(収賄罪)がまだ「疑い(嫌疑)」にすぎませんので、年休処理をすることには問題はないと思います。(3) 警察・検察での犯罪捜査が終ると、勾留期間限度内に起訴か不起訴かが決定されますが(刑事訴訟法247条、248条)、公務員が起訴されますと、休職となります(地公法28条2項2号)。
ですから、刑事裁判は、退職届出・辞職届出をしない限り、休職中の公務員として審理を受けることになります(4) 収賄罪で刑事裁判を受けると、犯情が強度に悪質でない限り、ほぼ執行猶予付きの懲役刑の判決がなされます。そのような判決を受けますと、地方公務員法16条の公務員の欠格条項「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることができなるまでの者」に該当します(懲役刑は「禁錮以上の刑」になります。)。その結果、地方公務員法28条4項「第16条の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く他、その職を失う。」という当然失職という取扱いとなります。
- 公務員の刑事犯罪(収賄罪)と分限・懲戒手続
(1) 刑事裁判手続中に、公務員の任命権者は分限又は懲戒手続をすることができるか。 公務員が犯罪を犯し刑事捜査・刑事裁判を受けているという事実がある場合、その犯罪行為は、公務員の身分保障手続の一環でもある分限手続の「その職に必要な適格性を欠く場合」(地公法28条1項3号)や懲戒手続の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」(地公法29条1項3号)にも該当することになるので、任命権者は、刑事裁判の確定(失職)を待たずに、人事処分としての分限・懲戒処分ができるかが問題となります。
ア. そもそも、刑事責任は、国家が司法手続きを通じて刑罰を科すものであり、他方、懲戒・分限責任は、労働関係において、人事権(任命権)を有する使用者が被用者に対して、任命権の範囲内で労働契約上の不利益を課すものであり、両者は別個の手続であり、それぞれ独自性を持つ責任を問題とするものでありますから、刑事裁判とは関係なく、職場において懲戒・分限手続を進めることは何ら問題はありませんし、刑事裁判の確定(失職)を待たずに懲戒・分限処分を出すことも可能です。
イ. 刑事裁判の確定(失職)を待たずに、人事処分としての分限・懲戒処分をする場合、処分に必要な「事実(犯罪事実や非行事実)」の確定をどのような手続で確定するのかが問題になります。新聞報道の記事だけで確定してよいでしょうか?懲戒機関と関係の無い第三者の調査結果である報道記事だけで処分することは懲戒処分の適正に欠けると思います。少なくとも、処分対象者からの弁解を聴取する必要はあります。しかし、当の本人は逮捕され警察留置場か拘置所に身柄拘束中です。時には、弁護人以外には面会できない接見禁止が付いている場合も多く、人事担当者が警察で本人に面会して事情聴取することもなかなか困難な場合が多いと思います。警察や検察庁の担当官に事情を聴取しようとしても、捜査の秘密ということで拒否されます。
ウ. そこで、一般的な懲戒手続のための事実調査としては、 <ⅰ>捜査期間中は、新聞記事等の収集や弁護人からの事情聴取を検討する。<ⅱ>起訴されて裁判になって公判傍聴をして法廷での本人(被告人)の弁解を聴取する。(裁判期日前に保釈で釈放された場合には、当の本人と接触して事情聴取することもできます。)<ⅲ>刑事裁判の判決宣告まで待って、判決の認定した事実に沿って、事実を確定する、という流れで、懲戒・分限手続の事実調査手続を考えて置きましょう。そういう意味では、刑事判決の確定より前の「判決宣告」時点で、判決文の内容となっている「事実」基準に懲戒処分をするということが、最も確実な事実認定による処分ということになるでしょう。
(2) 仮に、刑事捜査手続中又は刑事裁判手続中に、逮捕されている公務員本人が「依願退職(辞職届出)」手続をしてきた場合、どのような取扱ができるのでしょうか。依願退職手続を受理して退職させるのか、懲戒処分を実施するのかという問題です。
この点は、退職手当金を支給できるかできないかに影響しますので、次回に詳しく検討してみましょう。
公務員の刑事犯罪と法律(~収賄罪逮捕を中心に~):その2
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
- 公務員の逮捕時点での懲戒処分の可否と依願退職届出(辞職届出)の受理の可否
前回、刑事捜査手続中又は刑事裁判手続中に、逮捕されている公務員本人が「依願退職(辞職届出)」手続をしてきた場合、どのような取扱ができるのか(依願退職手続を受理して退職させるのか、懲戒処分を実施するのか)という問題を提起しました。今回はそれを検討していきましょう。(1) 公務員の辞職とは、「職員が自らの意思に基づき退職をすること」をいい、「依願退職」とも言われています。その申出(退職の同意)によって退職の発令(行政処分)が行われます。すなわち、退職願(申出)の法律的性質は、職員の任用が行政行為であると考えられていますので、その辞職、すなわち職を離れるについても任命権者の行政行為によらなければならないことになります。したがって、職員は、退職願を提出することによって当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願は本人の同意を確かめるための手段にすぎず、その同意を要件とする退職発令(行政行為)が行われてはじめて離職することとなるものである(高松高裁昭35年3月31日判決・行政裁判例集11巻3号796頁)とされています。
退職(辞職)届は、「任命権者は、職員から退職の申出があったときは、特に支障がない限り、速やかに、これを承認すべき(人事院規則8-2(職員の任免)第73条)であるが、行政執行に支障がある場合には退職を承認しないことも可能で、この場合には公務員関係は依然として存続することになる」と解されています。
この「特に支障がある場合」については、「職員を懲戒免職等の処分に付すべき相当の事由がある場合等がある」と解されており、「辞職が承認されるまでは職員は勤務する義務があるので、その期間を無断欠勤する場合は国家公務員法第82条又は地方公務員法29条の、懲戒事由の第1号および第2号に該当する」と解されています。(2) そこで、任命権者としては、刑事犯罪が問題となっている職員の依願退職届出を受理して辞職承認をすることは非常に難しいと思いますが、まだ刑事事件に至らないような犯罪嫌疑事案の場合には、後日、禁固刑以上の有罪判決の時に、退職手当金の返還請求をする(例・国家公務員法第15条~この退職後の退職返還規定は、地方公共団体の退職金条例にも引き継がれています。)ということを前提に、辞任届出の承認をすることもあり得ると思います。
しかし、公務員の逮捕にまで至ったほとんどの場合には、前述の「特に支障がある場合」すなわち、「職員を懲戒免職等の処分に付すべき相当の事由がある場合」として、辞任届出の承認をしないままで、懲戒手続を進めるという取扱いになる例が多いだろうと思います。当然のことですが、公務員が懲戒処分(懲戒免職)を受けて退職となった場合には、退職金支給制限規定(条例)が設けられており、退職手当金は支給されません。(参照・国家公務員法第14条~禁固刑以上の有罪判決の時に、退職手当金の支給はしないとの規定は、地方公共団体の退職手当金条例にも引き継がれています。)
- 収賄罪逮捕職員に対する退職金支給と住民訴訟
そこで、ある地方公共団体において、次のような取扱例がなされて住民訴訟になりました。収賄罪で逮捕された公務員職員を、懲戒処分ではなく、分限免職処分をして退職手当金を支給したのです。この事案の地方公共団体条例では、分限免職処分場合には、退職手当金は支払う規定になっており、有罪判決確定後でも退職金返還義務規定は定められていなかったということで、退職手当金を支給すると、地方公共団体の財産が退職手当金名目で不当に支出したままになるという特徴がありました。
最高裁昭和60年9月12日第1小法廷判決では、地方自治法に定められている「住民訴訟」の要件(例えば、違法対象行為は財務会計行為であることを要するとの要件等)からくる訴訟上の制約もあり、次のような判決内容になっています。(1) まず、懲戒免職処分にしなかったことが、住民訴訟の「財務会計行為の違法」となるのか。
この点については、判例は、「地方自治法242条の2の住民訴訟の対象が普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為又は怠る行為に限られるのは、同条の規定に照らし明らかであるが、右行為が違法となるのは、単にそれ自体が直接法令に違反する場合だけでなく、その原因となる行為が法令に違反し許されない場合の財務会計上の行為もまた違法となる。分限処分がなされれば当然に所定額の退職手当が支給されることとなっており、本件分限免職処分は本件退職手当金の支給の直接の原因をなすものというべきであるから、前者が違法であれば、後者の財務会計行為である退職手当金支給も当然違法となるものと解するのが相当である。」としています。註1註1:この判例理論は、それなりに肯首できるものなのですが、他方で、最高裁平成4年12月15日判決「一日校長事件判決」では、教育委員会が退職一日前に校長への昇給発令人事を行い、同日の退職により市が昇給をベースにした退職手当金を支給した事案で、「原因行為を行なった機関と財務会計行為を行なった機関が異なっており、前者が違法であれば、後者の財務会計行為である退職手当金支給も当然違法となるという関係にはない。」との判断をしている例もありますので、行政行為の先行行為と後行行為との間に直接的な原因結果の関係があるかは、個別的に判断されるものと思われます。
(2) 次に、懲戒免職処分にせずに、分限免職処分にしたことは違法なのか。
この点については、判例は、退職手当金支給の原因行為であった「分限処分」をしたことが違法であったかどうかを検討した結果、「当該職員の収賄事実が地方公務員法29条1項所定の懲戒事由にも該当することは明らかであるが、職員に懲戒事由が存する場合に懲戒処分を行うか否か、懲戒処分をするときにいかなる処分を選ぶかは任命権者の裁量に委ねられていることから、右の収賄事実のみが判明していた段階において、当該職員を懲戒免職処分に付さなかったことを違法であるとまで認めることは困難である。」「また、不適格な職員を早期に公務から排除して公務の適正な運営を回復するという要請に(分限処分で)応える必要のあることも考慮すると、本件分限免職処分が違法であるとすることはできない。」として、その後行行為である退職手当金支給も違法ではないとしています。(3) この判例の結論は、昨今のオンブズマン活動や住民監査の盛んな傾向からすると、退職手当金が支給されたままで放任される結果となるのですから、賛同できない面もあるだろうと思います。しかし、本件で問題となった地方公共団体では、その後、職員が逮捕された場合の退職手当金の支払い差し止めや、禁錮以上の刑に処せられた場合の退職手当金の全部又は一部の返納制度が条例で整備されたようですので、今後は、分限免職処分をして退職手当金を支払っていたとしても、その後、刑事裁判において「禁錮以上の有罪判決」を受けた場合には、退職手当金を返納することになるので、あながち、懲戒処分相当事案を、早期の時期に分限免職処分をしても違法ではないということで結果が不合理になることはないだろうと思われます。
*次回には、公務員の公金横領等の刑事犯罪と民事賠償責任の問題を考えてみましよう。
公務員の刑事犯罪と法律(~収賄罪逮捕を中心に~):その3
弁護士法人近藤日出夫法律事務所
弁護士 近藤 日出夫
公務員が刑事犯罪の収賄罪で逮捕された場合には、収賄行為によって経済的利得を得ていますが、贈賄者以外の第三者に損害を与えているわけではないので、民事賠償の問題は生じませんが、刑事犯罪が業務上横領罪(公金横領)の場合には、今まで述べてきた懲戒責任・刑事責任以外に、民事賠償責任も問題となってきます。公金が横領された結果、被害者である地方公共団体(市町村)に損失(損害)が発生しているからです。
そこで、刑事責任・懲戒責任と民事責任(賠償責任)について、簡単にまとめておきます。
- 公務員の犯罪と三つの法的責任
犯罪行為は、刑法などの刑罰法令に触れますので、刑事処罰を受けます。このことを「刑事責任」といいます。それ以外に、犯罪行為は、民法709条の「故意又は過失によって他人の権利を侵害した」という不法行為にもなりますので、被害結果に対する損害賠償責任を負います。このことを「民事責任(不法行為責任)」といいます。また、更に、行政上の資格や免許等の取消しなどの行政処分を受ける場合や雇用関係での懲戒処分などの個人の身分等に関する責任を負う場合もあります。これを、便宜上「その他の処分責任」と呼ぶことにします。 - 三つの責任の目的と峻別論
(1) 自己の行為に対して制裁を受けることを「責任」というのですが、その「制裁」は、ひとつの行為に対して(又は一人に対して)、ひとつの制裁を受けるということで成り立ってきたものと思われます。ローマ法時代でも民事責任・刑事責任(私的責任・公的責任等)の区別は明確ではなく、一元的責任(制裁)論であったと言われています。その後、ドイツ法の歴史の中で民事責任と刑事責任を分ける「民刑峻別(民刑分離)」の考え方が成立し近代法の姿になったと言われています。今の日本の法律は、この「民刑峻別論」の立場で規定されています。
(2) 刑事責任・民事責任・その他の処分責任の三つの責任は、民刑峻別論の立場(刑事責任と民事責任はそれぞれ制裁目的が異なるので、別々に責任を問うべきであるという立場)から、それぞれの責任をすべて一人の者(ひとつの行為)で負わなければならないという関係にあります。
刑事責任は、国家が処罰することで公共の秩序を維持し、犯罪が起こらないようにするための一般予防・特別予防を目的とする責任です。公金横領の犯罪の場合に、懲役刑に処して、その公務員が二度と犯罪を犯さないように戒め(特別予防)、更に、そのことを知った他の公務員に対して公金横領すると懲役刑で処罰しますよと警告している(一般予防)わけです。 民事責任は、損害を公平に分担するための衡平的正義の実現を目的とする責任です。公金横領の犯罪の場合に、横領金については、その分地方公共団体の公金が減っていて損害が生じており、その反面横領犯人である公務員はその分を領得していますので、損害を公平に分担する方法として、地方公共団体は、横領犯人に対して横領金相当の損害賠償を請求する権利があり、横領犯人は損害を賠償する責任があるとするわけです。 その他の処分責任としては、既に検討した雇用関係での制裁となる懲戒処分(退職金不支給処分)などがありますが、これは、国民全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない行為をしたという理由で、かかる公務員の地位保障(地位喪失)の目的からくる制裁です。
(3) 以上の理由から、公務員が公金を横領した場合には、業務上横領罪として刑事責任を問われ(懲役10年以下・刑法253条)、民事責任として横領金相当の損害賠償責任を負い(不法行為責任・民法709条)、その他の処分責任として懲戒免職処分又は失職(地方公務員法)となります。
- 三つの責任の相互影響の有無
以上の三つの責任は、それぞれ別個に全部負わなければならないという法制度ではあるのですが、新聞・テレビ等のマスコミ・ニュースなどで、「横領金は全額返済しているため、刑事告訴は見合わせる方針である。」とか、「刑事判決では、被害弁償を実施していること、既に免職となって一定の社会的制裁を受けているという理由で執行猶予判決となった。」とかいう報道がなされている場合があります。それぞれの三つの責任の間には、何らかの相互影響があるのでしょうか。最後に、この点を検討してみましょう。
(1) 民刑峻別論の立場からは、本来は三つの責任の間には、何ら影響はないことになります。それぞれの責任の目的が違うからです。
(2) しかしながら、刑事裁判では、量刑判断事情として民事責任の履行の有無、懲戒処分等の他の制裁の有無を考慮する実務になっています。被害者等との被害弁償示談が成立すれば量刑は軽くなってきます。懲戒免職処分を受けて公務員の地位を失っているので執行猶予とすると判決理由で示される場合もあります。更に、民事賠償制度においては、「懲罰的慰謝料制度」を認める国もありますが、日本では採用されていません(最高裁第2小法廷1997年7月11日判決民集51巻6号2573頁-萬世工業事件判決)。「懲罰的慰謝料制度」とは、民事の損害賠償責任の中で、個人間での損失補填以外に罰則的な金額を慰謝料として個人間で支払わせるという刑事的(罰金制度)な意味合いが含まれた制度です。
これらは、民刑峻別論とは対比される制裁一元化理論(民刑一元化論)というべき考え方になります。
このような取扱いがあることから、社会的に最も重い責任と思われる刑事責任に対しても、「民事責任と懲戒処分責任を負ってもらえれば、刑事告訴まではしない。」という現実的な取扱いもなされているわけです。逆に、民事責任としての横領金相当額の返済ができないのであれば、刑事裁判を通じての重たい刑事責任を負ってもらうということになるわけです。被害者の立場からは、厳重な刑事処罰を求めるために、刑事裁判が終るまでは、横領犯人や弁護側からの被害弁償金(一部弁償が多い)は受け取らず、刑事裁判が終ってから民事賠償責任を求める(弁償金の受領する)取扱いをすることも可能です。なお、刑事責任・民事責任・その他の処分責任の三つの責任は、それぞれ目的が異なり処分する主体も異なる場合があります(公金横領の場合には、刑事責任追及者は国家又は警察、民事責任追及者は被害者である地方公共団体、懲戒処分追求者は使用者である地方公共団体の長)ので、すべてを追求しなければならないものではなく、処分する主体側の判断で、任意の責任追及の判断がなされます。この意味でも、民事責任だけ追及され、刑事責任は追及されなかった場合や、懲戒処分責任は追及されずに民事責任だけ追及されたという例が多く発生するわけです。
(3) 最後に、公金横領のように被害者がいる犯罪では民事賠償責任を履行することが刑事裁判の量刑を軽くできる事情として考慮されるのですが、収賄罪のように被害者がおらず被害弁償相手がいない場合にはどのような量刑事情が考えられるでしょうか。収受した金銭を贈賄者に返還するということもあるでしょうが、これは被害弁償ではありません(刑事裁判の中で、不当な取得金として没収又は追徴されます)。刑事実務としては、犯罪被害者が存在しない社会的法益侵害の犯罪(覚醒剤事犯や道路交通法違反など)のような場合には、社会福祉団体等に「贖罪寄付(しょくざいきふ)」をして社会に還元することで、被害弁償の履行と同様の量刑事情として考慮する運用例もあります。「贖罪寄付」は、宮崎県内では、社団法人宮崎県犯罪被害者支援センター(0985-38-7831)や宮崎県弁護士会法律援助基金(0985-22-2466)等が受け付けています。
以 上
TEL:0985-27-7711 FAX:0985-20-1271
Copyright© 宮崎県町村会 All rights reserved.
本ホームページに掲載されている文章、写真、その他のすべての情報の著作権は、宮崎県町村会が保有しています。